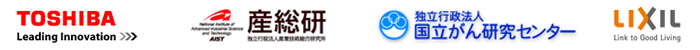1. リコピン
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報
2. リコピンの用途
2.1. リコピンの応用分野、川下製品
3. リコピンの製造法
4. リコピンの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明
5. 世界のリコピン市場
5.1. 一般的なリコピン市場の状況、動向
5.2. リコピンのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. リコピンのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. リコピン市場予測
6. リコピン市場価格
6.1. 欧州のリコピン価格
6.2. アジアのリコピン価格
6.3. 北米のリコピン価格
6.4. その他の地域のリコピン価格
7. リコピンの最終用途分野
7.1. リコピンの用途別市場
7.2. リコピンの川下市場の動向と展望
リコピンは、CAS番号502-65-8で知られるカロテノイド色素の一種であり、主に赤色の色素として機能します。この化学物質は、トマトやスイカ、ピンクグレープフルーツなど、多くの赤色果物や野菜に自然に存在し、その抗酸化特性が健康に良い影響を与えるとされています。リコピンは脂溶性の物質であり、その構造は11個の共役二重結合を持つ直鎖のポリエンから成ります。この構造により、紫外線や可視光線を吸収し、抗酸化作用を発揮します。
リコピンの主たる用途の一つは食品産業における天然色素としての利用です。食品に自然な赤色を与えることができるため、ケチャップやジュース、ゼリーなど様々な加工食品に使用されます。また、抗酸化作用による健康効果が期待され、ダイエタリーサプリメントや栄養補助食品としても広く利用されています。これにより、心血管疾患や特定のタイプの癌、そして老化関連疾患のリスク低減に寄与する可能性があります。
リコピンにはいくつかの異性体が存在し、その中でもトランス型とシス型が広く研究されています。天然のリコピンは主にトランス型ですが、加工することによりシス型への異性化が進むことが知られています。シス型は生体利用率が高いとされ、より多く吸収されることが研究で示されています。
リコピンの製造方法には自然抽出が一般的で、特にトマトが主要な供給源となっています。また合成による方法もありますが、コストの問題から主には自然抽出が好まれています。トマトからの抽出は、まず原料を加熱し、溶媒抽出法を用いてリコピンを分離するというプロセスを含みます。その後、純度を上げるために再結晶化やクロマトグラフィー技術が使用されます。
関連技術としては、リコピンの安定性を向上させるためのマイクロカプセル化やナノエマルジョン技術が挙げられます。これらの技術は、リコピンの酸化を防ぎ、摂取時の生体利用効率を向上させるためのものです。特にナノテクノロジーは、より効果的な地位を占めており、食品や医薬品の分野での使用が促進されています。
安全性の面では、リコピンは一般的に安全性が高いとされています。食品として摂取する量では副作用はほとんど報告されていませんが、過度の摂取により皮膚がオレンジ色になる「リコペニア」という状態になる可能性があります。また、アレルギー反応の可能性もゼロではないため、摂取に際しては過度に心配する必要はないものの、注意が求められます。
リコピンに関連する特許や技術は、各国でさまざまに登録されており、特に製造方法や抗酸化作用を活用した健康食品の開発に関するものが多く見受けられます。特許は、新しい抽出技術やその利用法、効果的な異性化の方法、さらにはリコピンを使った組成物に関するものが中心です。
こうした多角的な利用と性質があるリコピンは、健康維持や美容、食品産業、さらには製薬分野でも有望な素材としてますます注目を集めています。その天然由来で体に優しい特性と、多様な効果は今後もさらに研究が進められ、利用範囲が広がっていくことが期待されます。
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer